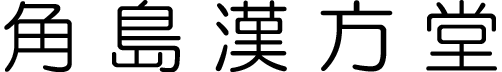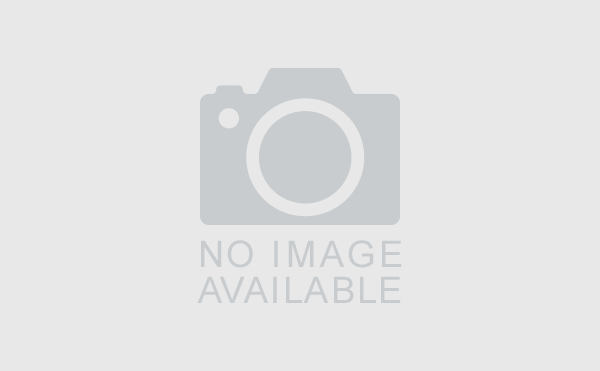こんにちは、角島漢方堂です。 春は体調を崩しやすい季節です。
学的に説明すると、春は「肝」の季節とされています。東洋医学では、五行説に基づいて自然界と人体を結びつけ、季節や環境に合わせて体調を整えることが重要だと考えられています。
春と「肝」の関係
春は肝臓に関連しており、肝の働きが最も活発になる時期です。肝は血液を調整し、気(エネルギー)の流れをコントロールする役割があります。春になると、自然界のエネルギー(陽気)が上昇し、生命力が活発になりますが、それに伴い、肝の機能が強く働くため、以下のような不調が起こることがあります。
- 肝気の上昇
春は「肝気」が上昇しやすい時期です。これが過剰に働くと、肝のエネルギーが上向きになり、精神的なイライラやストレス、怒りっぽくなることがあります。このような精神的な不調が体調に影響を及ぼし、消化不良や頭痛、目の疲れなどが現れることがあります。 - 気の滞り
肝は気の流れを調整する役割を果たしますが、春に気温が変動したり、天気が不安定だったりすると、外部の影響で体内の「気」の流れが滞りやすくなります。これにより、体調不良や疲れやすさ、倦怠感などが生じることがあります。 - 肝血の不足
春は「肝血」の不足によっても体調不良が引き起こされることがあります。特に、冬の間にあまり養生ができなかった場合や、寒さから解放されて活動的になりすぎた場合に肝血が不足し、めまいや肌荒れ、目のかすみなどが起こることがあります。
春の不調を防ぐためには
- 規則正しい生活
春は活動的になりやすいですが、過度に働きすぎたりストレスを溜めたりしないよう、規則正しい生活が大切です。 - 適切な食事
春は「酸味」が肝に良いとされていますので、レモンや梅干しなどの酸味のある食品を取り入れると、肝のエネルギーをうまく調整できます。 - リラックスする時間を持つ
春は精神的に不安定になりがちな時期でもあるため、深呼吸や瞑想、軽い運動で心と体をリラックスさせることが大切です。 - 肝をケアする食材や薬草
春に良いとされる食材には、例えば「春菊」「タケノコ」「豆苗」などがあり、これらは肝の働きをサポートします。また、薬草としては「柴胡(サイコ)」が肝気を調整するためによく使われます。
春は自然界の変化とともに、体の中でも「肝」が活発に働き、体調に影響を与える時期です。これをうまく乗り越えるためには、心身のバランスを意識し、無理をせず、調和を大切にすることが求められます。
春に起こる身体の不調ベスト10
1位__ 昼間眠い
2位__ 身体がだるい
3位__ イライラする
4位__ 肩がこる
5位__ 気分が落ち込む
6位__ ゆううつ感
7位__ 倦怠感
8位__ 目覚めが悪い
9位__ 不安感
10位_ 腰痛
ここでは、春に適した食材をいくつか挙げ、それぞれの東洋医学的な視点からの効果を解説します。
1. 春菊(しゅんぎく)
春菊は春の旬の野菜で、肝を養うとされています。特に、春菊には「肝気」を巡らせる働きがあり、気の滞りを解消し、ストレスやイライラ、精神的な不安定さを和らげる効果があります。また、春菊は「清熱」の作用もあり、体内の余分な熱を冷まし、春先の乾燥による皮膚のトラブルにも良いとされています。
- 効能: 肝気の流れを整える、ストレス解消、清熱
2. タケノコ
タケノコは春の代表的な食材で、東洋医学では「肝を養う」「気を巡らせる」食材として重宝されています。タケノコは、肝のエネルギーを助け、体内の滞った気を流すのに有効です。特に、春に多く食べることで、季節の変わり目に起こりがちな気の滞りや倦怠感を解消します。また、タケノコには「利水」作用があり、体内の余分な水分を排出する手助けをします。
- 効能: 肝気を巡らせる、気の滞りを解消、利水作用
3. 豆苗(とうみょう)
豆苗は春に育つ若い豆の芽で、肝を強化する作用があります。豆苗は「肝血」を補い、肝の働きをサポートする食材として優れています。また、肝血が不足すると目のかすみやめまいが生じやすいので、豆苗を食べることでこれらの不調を和らげることができます。豆苗は清涼感があり、春の温暖な気候にぴったりな食材です。
- 効能: 肝血を補う、目の疲れを解消、清涼感
4. ウド
ウド(山ウド)は、春の野生の食材であり、肝の働きを助けるとともに、体内の気の流れを良くする効果があります。ウドは「肝気」を活性化させ、ストレスや怒りを抑える効果があり、体内の不調を改善するのに適しています。また、ウドには利尿作用もあり、余分な水分を排出するため、むくみや便秘にも良いとされています。
- 効能: 肝気を活性化、ストレス解消、利尿作用
5. 梅干し(うめぼし)
梅干しは、酸味が特徴的で、東洋医学では「肝」を強化する食材として広く使われます。酸味は肝気を調整し、気の滞りを解消するため、春の不調を和らげます。また、梅干しには「清熱」や「解毒」作用もあり、体内の熱を冷ますので、春の温暖な気候に合います。さらに、梅干しには消化を助ける効果もあるため、食欲がないときにも最適です。
- 効能: 肝気を調整、清熱、消化促進
6. レモン
レモンは酸味が強く、梅干しと同じく肝に良いとされています。レモンの酸味は肝気を調整し、気の滞りを解消する働きがあります。また、レモンには豊富なビタミンCが含まれており、春先の肌荒れや免疫力低下を防ぐ効果もあります。さらに、レモンには消化を助ける作用があり、春の食欲不振にも有効です。
- 効能: 肝気を調整、消化促進、免疫力向上
7. 人参(にんじん)
人参は東洋医学で「脾(ひ)」を強化する食材として知られていますが、春に食べると肝のエネルギーをサポートする効果もあります。特に、肝血が不足しているときに人参を摂ると、血を補うと同時に肝の働きを助けることができます。春の寒暖差による体調不良に対しても、人参は身体を温める作用があり、調子を整えます。
- 効能: 血を補う、肝の働きをサポート、体を温める
8. 春キャベツ
春キャベツは「清熱」や「解毒」の作用があり、春の不調を改善するのに適しています。特に春キャベツは柔らかく、消化が良いため、胃腸が弱っているときにも食べやすい食材です。また、春キャベツは肝の働きをサポートする効果があり、体内の余分な熱を冷まし、腸内の環境を整える働きもあります。
- 効能: 清熱、解毒、消化促進
春の体調不良を防ぐ食材のまとめ
春に適した食材は、肝のエネルギーを調整し、気の流れを良くするものが多いです。これらの食材は、体の内外のバランスを整え、春特有の不調を和らげるのに役立ちます。特に、肝気の滞りや肝血の不足を補うことで、イライラや倦怠感、消化不良、目の疲れなどを改善できます。
春の不調を和らげるためには、これらの食材をバランスよく取り入れて、心と体の調和を保つことが大切です。
お悩みの症状やご相談がありましたら
お電話やメッセージで
ご予約を頂ければ、
しっかりとお話をお聞きした上で
漢方薬のご提案をさせて頂きます。
是非ご利用下さいませ!
ひとり一人の体質、
症状に合わせた漢方薬で健康をサポート致します!
神奈川県川崎市中原区新丸子町747
044-874-0709
10:00〜19:00
定休日:土曜日・日曜日・祝日
#頭痛 #動悸 #肩コリ #関節痛 #冷え性 #睡眠障害頻 #耳鳴り #女性特有のお悩み #不妊症 #自律神経失調症 #更年期障害 #口渇 #皮膚病 #ダイエット #便秘 #風邪をひきやすい #しびれ #頻尿 #眼精疲労 #虚弱体質 #体質改善 #添加物が心配 #野菜不足 #漢方 #漢方薬 #漢方相談 #花粉 #アスリート #起立性調節 #タウロミンなど